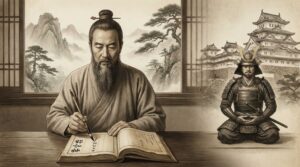昔の政治家 / 今の政治屋
長野の山奥より、宮司の独り言
昔の政治家と、いまの政治屋。
その根本的な違いについて、好き勝手に述べてみたい。あくまで山深き社に暮らす一人の神職の戯言、耳を貸すも聞き流すも、皆様次第ということで。
境目は「戦前」と「戦後」に置いてみる。
とはいえ、戦前がすべて尊く、戦後がすべて悪いなどというつもりはない。ただ、日本人の精神や政治の根っこが、大きく変わったのはこの時期だったと思うからだ。
昔の政治家…己を捨て、国に殉ずる覚悟
昔の政治家は、政治に身を投じるとは、すなわち私財をなげうつことだと心得ていた。
家を売り、土地を手放し、蓄えも名誉もすべて投げ出して、国と民に尽くす…それが当然の姿であり、美徳だった。
政界を去ったあと、財産はおろか名刺一つ残らなかった者もいた。しかし、その人の生き様だけは語り継がれた。
「死して皮を残す」…まさに陰徳の人。美田を児孫に残さず、志を国に捧げた者たちである。
そして何より、彼らは国家の安寧と国体の護持を己が使命と信じていた。
政治家たるもの、いかなる局面でも命を張る覚悟を持たねばならぬ。
「政治は命懸け」、それが昔の政治家の矜持だった。
西郷南州、大久保利通、そして昭和の激動の中で殉じた英霊たち。
彼らが今の日本を見たら、果たしてどう嘆くだろうか。
今の政治屋…金と地位に憑かれた俗物たち
今の「政治屋」はどうか。
政治とは「食い扶持」となり、「金儲けの手段」と化した。
企業献金、便宜供与、袖の下。表では「政治団体」、裏では不動産や資産操作。
親族名義で財産を隠し、莫大な富を蓄え、「世襲」という名の利権譲渡を当然とする。
そして、「国民のため」とうそぶきながら、守っているのは自分の生活と地盤だけ。
領土問題も、拉致問題も、占領憲法も放置したまま。
選挙に勝つための看板スローガンは「国民主権」だが、実際には国民を欺き続けている。
新幹線はただ乗り、会議はリゾート地、国民の税金で贅沢三昧。
「先生」と呼ばれて上機嫌になり、湯水のように血税を無駄遣い。
挙げ句の果てには、かの江沢民の銅像を日本国内に建てようとまでした。
これで「国民のため」と言うのだから、笑わせるにもほどがある。
昔の政治家…堂々たる覚悟と胆力
かつての政治家は、「質実剛健」を尊び、姑息な手法を嫌った。
国家の一大事には正面から挑み、己が命を懸けて事に当たった。
尖閣が危ない、竹島が危ない、対馬が危ない…
そのような危機があれば、彼らは口先で叫ぶのではなく、現地に赴き、腹を括った。
死を覚悟してでも守るものがあるという強さと覚悟があった。
いま、そのような胆力をもつ政治家がどれだけいるだろうか。
せいぜい西村真悟氏のような一握りの者が、かろうじて気骨を保っているのみである。
今の政治屋…次の選挙と自己保身しか頭にない
彼らが考えているのは、次の選挙でどう勝つか、それだけ。
右も左も、保守も革新も、結局は金集めに躍起となっている。
国民が生活に困窮していようと、増税にあえいでいようと、そんなことは見えていない。
選挙で落選したかと思えば、比例区でゾンビのように復活。
もはやこの国の選挙制度すら、彼らにとって都合の良い温床でしかない。
嘆かわしいのは、それを許しているのが国民自身だということ。
政治家に怒りをぶつける前に、選ぶ側の覚悟が問われている。
石破内閣の腐敗は誰の目にも明らかだ。
それでも誰も辞職を迫らず、誰も立ち上がらない。
高市早苗氏も、麻生太郎氏も、引きずり下ろすことができない。
自民党という大樹は、もはや内側から腐り果て、再生不能な状態にある。
国民は、ただ嘆き悲しむのみ。
おわりに
これらは、長野の山奥に鎮まる一人の宮司の独り言である。
だが、「昔」と「今」の間に横たわる断絶を、私は見逃すことができない。
政治とは、国家と国民の未来を託す営みである。
それが私利私欲にまみれた者どもに蹂躙される姿を、どうか放置せぬでほしい。
国を憂い、民を守るという志が、再びこの国の政治に宿らんことを。
ただ、静かに願うばかりである。