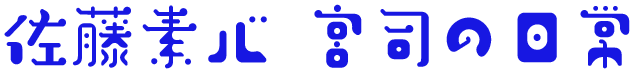神道の生きざまに学ぶ

神職としての道を歩み始めたきっかけは、阪神淡路大震災であった。もともとは機動隊の特殊部隊に所属し、警察官として治安維持の任にあたっていたが、あの未曾有の震災を通して、「人間はいかに生き、いかに死ぬべきか」という問いに直面し、神職としての生き方に導かれた。
最も尊敬し、導いてくださった恩師は、小林美元先生と春日大社の葉室宮司である。葉室宮司とは、大阪国学院の先輩後輩の関係にあり、医師から神職に転じた異色の経歴を持つ。宮司もまた、警察官から宮司となった異色の道を歩んだ。
葉室宮司と共に過ごした春日奥山「月日亭」での対話は、今も心に深く残っている。彼は常に、「科学や医学を盲信してはならない。マスコミの報道も鵜呑みにすべきでない」と語り、特にワクチンや薬に関しては慎重な姿勢を貫いていた。人間には本来自然治癒力が備わっており、それを損なうことは、神の意志に背く行為であると説いた。
また彼は、警察官への信頼について話が及ぶと、「警官の中で最も信頼できるのは、警察犬だけ」と笑いながら語った。宮司も元警官として、「本物の警察官は、国民のために行動する。上司や点数稼ぎのためではない」と共感し、警察官としての真の使命を再確認する機会となった。
葉室宮司はまた、宇宙の起源や人類の成り立ちについても情熱を注いでいた。人間の祖先が海辺に打ち寄せたカビの胞子であり、雷によって生命が芽生え、魚から恐竜、そして人間へと進化したという壮大な話を、真剣な面持ちで語っておられた。その話を聞きながら、自然と人間の繋がりの深さ、神意の不思議さをあらためて感じた。
神道の根本にある死生観は、「生きている」と「生きていく」の違いにある。葉室宮司はよく、「生きていくためには智慧が必要だ」と話していた。すべての動物はただ生きているが、人間は智慧をもって他者のために生きることができる。これは、神より与えられた最大の恩恵であり、人間の本質を表している。
神道では、人の死を「帰幽」と呼ぶ。すなわち、神の世界に帰ることである。霊魂は「幽世」へ帰り、やがて祖霊として子孫を見守る存在となる。この世での役目を終えた後も、神の御許に仕え、家族や国を見守る。これは神道が説く「いのちの連続性」であり、生と死の境界を越えたつながりを意味する。
宮司自身も、脳梗塞により死線をさまよった経験がある。18時間にも及ぶ手術の中で、身体はふわりと浮き、雲を抜け、花畑を見下ろしながら飛んでいた。亡き母の姿が遠くに見え、呼び戻す家族の声が響いた。あの体験は、魂の存在と死後の世界を確信させた。
神道の葬送儀礼である神葬祭は、亡き人を祖神として祀る神聖な儀式である。霊魂は清められ、祖霊として家の守護神となる。この考え方は、日本書紀や古事記、風土記などに見られるように、古代から連綿と受け継がれてきた。
「死者を鞭打たない」のが日本人の精神であり、「悪しき者も死ねば神となる」ことを受け入れてきたのが日本の文化である。靖国神社を分祀しようとする行為や、死者を非難し続ける態度は、日本人の精神から大きく外れている。
神道では、この世を「現世(うつしよ)」と呼び、人は神から生まれ、神に帰っていく存在と考える。この考えは、祖先崇拝、自然崇拝、そして人と神とのつながりの中で育まれてきた。人は肉体を離れても、その魂は消えることなく、常に子孫と共にある。
いのちは連綿と流れ、祖先の命が今の自分につながり、また子孫へと受け継がれていく。科学的にはとらえきれないこの生命の流れこそ、神道の核心にある「死生観」である。目に見えず、手に取ることのできないものを信じ、敬い、共に生きる。そこにこそ、日本人が誇るべき精神が息づいている。