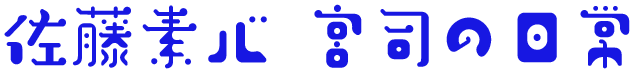霊能真柱(たまのみはしら)を仰ぐ。神ながらの道を歩む心

神道の根本とは何か。古来より人々はこの問いに向き合ってきた。学問の進化や時代の移ろいの中で、人はしばしば「神」を遠ざけ、「霊」を忘れ、「生」と「死」を切り離して考えるようになった。しかし、古神道はそのすべてを一つの循環として見つめている。生も死も、神も人も、見える世界と見えざる世界も、互いに響き合い、支え合う。
小林美元先生に学んだ折、「平田篤胤を読め、佐藤信淵を学べ」と幾度も教えを受けた。とりわけ師は「霊能真柱(たまのみはしら)」を深く読み込めと諭された。篤胤は霊界を直視し、神々と人との交感を実学として説いた復古神道の巨星である。彼の言葉にある「幽世(かりよ)こそ本世(もとよ)」とは、死後の世界こそが本来の生命の源であり、現世はその映しにすぎないという意味を持つ。
人は死して終わるのではない。霊魂は幽冥界に赴き、しばし静まり、やがて新たな肉体を得てこの世に還る。これを「鎮まりの道」とも言う。現世に残された者を守護しつつ、再び命の環に加わる。その循環が永遠に続くのが神ながらの理である。死を恐れるのではなく、死を通して生命の尊さを知る。これが古神道の核心にある思想である。
篤胤は文献のみに頼らず、自らの感得によって神界・霊界を学問の対象とした。異界を迷信として退けず、むしろ真理の根にあるものとして探求した。その姿勢こそ「霊能真柱」と呼ばれる所以である。神を信じるのではなく、神と共に考え、神の理を自らの心に映す。そのような在り方を篤胤は生涯かけて示した。
古神道の言葉に、「古言を通じて古事を知り、古意を明らかにして古道に至る」とある。古(いにしえ)の言葉に耳を傾けることは、神々の思いを知ることにほかならない。古道とは、古きを懐かしむことではなく、永遠の真理に通じる道を意味する。現代の人々が見失いつつあるものを、古神道は静かに照らしている。
神職の務めとは何か。それは、祭祀を執り行うことだけではない。神々と人、現世と幽世、可視と不可視の間を結ぶ「真柱」となることにある。霊の流れを読み取り、神の息吹を感じ取り、世に安寧をもたらすために祈る。大切なのは「大和心を固める」ことである。大和心とは、調和を尊び、誠を尽くし、他を生かして己を立てる心だ。そこに神の光が宿る。
篤胤の学問は、庶民にも深く浸透した。難解な理屈ではなく、生活に根ざした祈りと信仰を言葉にしたからである。村人の心を照らす神話の再解釈、死者の魂を慰める教え、それらは人々の心を温め、日本人としての誇りを呼び覚ました。彼の思想が明治維新という国の大転換を導いたのは偶然ではない。人々が「天とつながる道」を信じたからこそ、国が目を覚ましたのである。
古神道の学びは、ただ古い書物を紐解くことではない。それは、日々の祈りの中に生きている。朝の光に神を感じ、夕暮れの静寂に祖霊を思い、他者の幸せを祈る。その一つ一つが、古道に通じている。
霊界を語ることは、見えないものへの畏れを思い出すことだ。科学や合理の時代にあって、見えぬものを軽んじる風潮がある。しかし、見えぬものこそが世界を支えている。風は見えずとも木々を揺らし、祈りは見えずとも人の心を変える。神道とは、その「見えぬ力」を尊び、感応する道である。
平田篤胤が説いたように、神は遠くにいない。神はわれわれの内にあり、われわれの息の中にある。古神道とは、その神性を思い出す学問であり、修行であり、祈りである。
いまの時代こそ、古神道の灯が再び必要とされている。物質の豊かさに溺れ、心の拠り所を見失いがちな現代にあって、人が人としての尊厳を取り戻すには、「霊の理」に立ち返らねばならない。神ながらの道とは、自然と共に生き、祖先に感謝し、未来に責任を持つ生き方である。
篤胤が残した言葉を読み返すたびに思う。日本は、神と共に歩む国である。霊魂の循環を信じ、天地の調和を尊ぶ民族である。この精神が絶えぬ限り、日本は決して滅びない。
祈りとは願いではなく、誓いである。「神ながらの心」を忘れぬ限り、わたしたちはいつでも神の御光に導かれている。それを信じ、今日も祝詞を奏でる。霊能真柱の光が、すべての人の胸に立つことを願って。