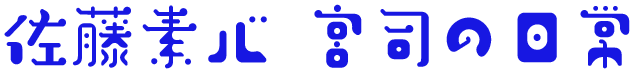学力より、人としてのぬくもりを教えよう

宮司は、戦後の教育が子どもたちの心をどこへ導いてきたのかを思う。便利さや効率ばかりを追い、人としての誇りや感動を忘れてしまった社会の姿を見つめるとき、そこにあるのは「豊かさ」という名の空虚さである。子どもたちは知識を詰め込まれ、競争に駆り立てられながら、いつの間にか心を置き去りにしてしまった。だが、それを嘆くだけでは何も変わらない。教育とは、家庭から始まるものだ。
学校の先生に任せきりでは、人の温もりは育たない。親が語り、祖父母が伝える中で、子どもは「日本人の心」を学ぶ。昔のように、夜の囲炉裏のそばで祖父が語る戦中の話、祖母が教える季節の行事、その一つ一つが生きた教育であり、文化の継承であった。今、その火が消えかけている。親も祖父母も、まず自らの口で語る責任を取り戻さねばならない。
学問や語学も大切だが、それ以上に教えるべきは「人のために涙を流すこと」である。人を思い、恥を知り、他人の苦しみを感じ取れる心を育てることが、真の教育だ。これを失ったとき、国は形を保っていても魂を失う。宮司は、戦後教育がその魂を薄めてきたことを深く憂えている。
二宮尊徳の教えは「道徳なき経済は罪悪なり」という言葉に尽きる。損得の前にあるのは「人の道」だ。楠木正成が命を懸けて守ったのは、単なる王政ではなく、忠義と誠の心だった。そうした生き方を知らずに、「まさなり」と呼び間違える現代の子どもたちの姿は、日本が自らの根を見失っている証である。
親が教えねば、誰も教えない。祖父母が語らねば、子どもたちは真実を知ることができない。神社で手を洗う作法や拝礼の姿勢は、単なる形式ではない。心を清め、感謝を表す日本人の祈りの形である。その意味を伝えるのは、親の務めであり、祖先への敬意を継ぐ行為でもある。
英語が話せなくても、立派に生きることはできる。大切なのは「思いやり」「勇気」「調和」という、人間の根を支える三つの徳だ。それは、かつて日本人が自然とともに生き、互いに助け合いながら築いてきた文化の結晶でもある。
宮司は願う。子どもたちが再び、誰かのために汗を流し、涙を流し、命の尊さを知る時代が戻ることを。日本の教育は、制度でも教科書でもなく、家庭の中の温かな教えから始まる。その火を絶やさぬことこそ、親として、そして日本人としての最大の責任である。