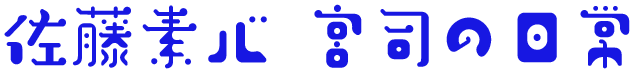新嘗祭に息づく日本の心を未来へ

宮司は、本日「新嘗祭」を齋行し、新穀と神酒を謹んでいただいた。毎年同じ儀式でありながら、この日の空気は不思議と凜としており、今年も稲の恵みを授かったという深い感謝が胸に満ちてくる。今日という日は、単なる「勤労感謝の日」ではなく、日本古来の「新嘗祭」の日であるという原点を、改めて強く意識させられる。
祭典の最中、宮司の脳裏には古い記憶がよみがえった。それは、2009年に産経新聞「風の間に間に」で皿木喜久氏が綴った「新嘗祭」の記事である。今朝読んだわけではない。だが、毎年この日を迎えるたびに、当時の文章がふっと心に浮かび上がる。それは、日本が戦後に失ったものの大きさを静かに示す内容だったからだ。
戦後、GHQが「神道指令」を発し、日本の祝祭日の意味を大きく書き換えた。皇室の祭祀を「私的行事」と位置づけ、国民から切り離した。その結果、祝祭日の本来の意味は曖昧化し、日本人自身も自国の文化の核心を言葉にできなくなった。
「なぜ、明治天皇のご生誕の11月3日が文化の日なのか」
「なぜ春季皇霊祭が春分の日なのか」
「そして、なぜ新嘗祭が勤労感謝の日に置き換えられたのか」
これらは決して小さな問題ではない。
宮司は、この断絶こそが戦後日本の精神喪失の始まりだったと感じている。
本来、新嘗祭は天皇陛下が新穀を神々にお供えし、みずからも召し上がられる最も重要な祭祀であった。米を育て、収穫し、その恵みに感謝し、翌年の豊穣を祈る。この「祈りの循環」は、日本という国が古代から守ってきた魂の営みである。
しかし、祝祭日が書き換えられたことで、日本人自身がその意味を見失い、結果として、宗教でも政治でもない「文化としての天皇」の姿さえ見えにくくなってしまった。宮司は、ここにこそ戦後の日本が抱える深い問題があると考えている。
一方、日本の各地では、天皇の祭祀に通じる民俗行事が今も息づいている。奥能登の「アエノコト」など、新穀を神に供え、共に食する風習は全国に残っている。稲穂を尊び、自然を畏れ、恵みに手を合わせる姿は、日本人が本能的に持っている精神文化の表れだ。
宮司は、天皇陛下が毎年「お田植え」や「稲刈り」をされる理由も、まさにこの稲作文化を体現し、未来へ伝えるためだと受け止めている。
しかし現代では、稲作は厳しい状況に置かれ、日本の食料自給率は危険なほど低下している。だからこそ、新嘗祭の意味を思い出し、日本人が稲作を中心に社会を築いてきた歴史を再び学び直す必要がある。
新嘗祭は、単なる「収穫への感謝」ではなく、日本人が自然とともに生きてきた証そのものだ。祖先への感謝、天地への畏敬、そして国家の安寧を祈る日でもある。戦後の混乱で奪われたものは大きかったが、再び取り戻すことはできる。その第一歩は、「本日の意味を知ること」から始まる。
宮司は、新嘗祭こそ、日本人が日本人であることを思い出させる最も尊い日だと信じている。稲穂の輝きは祖先からの声であり、新穀の白さは日本の心そのものだ。そして、神々とともに食すという伝統は、未来へと受け継ぐべき約束である。
日本が何を守り、何を誇るべきか。その答えは、静かな新嘗祭の祈りの中にこそ宿っている。