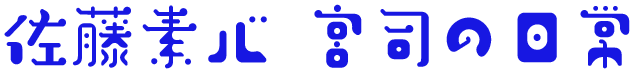ゆずり葉に託された日本の心

宮司は、正月が近づくたびに「ゆずり葉」という言葉と、その静かな姿を思い起こす。楪は声高に主張することなく、ただ時が来れば古い葉が落ち、新しい葉へと命を託す。そのあり方は、日本人が古来より自然の中から学び取ってきた、生き方そのものを映している。
ゆずり葉は、正月の輪飾りや鏡餅に添えられる。そこには単なる装飾以上の意味が込められている。新年とは、何かを新しく得る時であると同時に、何かを次へ手渡す時でもある。古い葉は自らを誇らず、未練も残さず、静かに地へと還る。そしてその葉は、やがて土となり、次の命を育む糧となる。宮司は、この循環こそが日本の精神の根幹であると考える。
河井酔茗の詩が語る「譲られるもの」は、物質だけではない。文化、言葉、作法、信仰、そして生きる姿勢である。親が子に譲り、子が孫に譲るものは、目に見える財よりも、むしろ目に見えぬ心である。太陽が巡る限り絶えることなく受け渡されてきたものが、日本という国を形づくってきた。
時代は、江戸から明治へ、明治から大正へ、大正から昭和へ、昭和から平成へ、そして令和へと移り変わった。その移ろいは、断絶ではなく継承である。前の時代を否定して次が始まったのではない。先人の歩みを土台として、新しい時代が芽吹いてきた。ゆずり葉がそうであるように、古いものが完全に消え去ることはない。地に還り、次を支える力へと姿を変える。
現代は、変化の速さゆえに、切り捨てることが進歩であるかのように語られがちである。しかし宮司は、切り捨てるだけの社会に未来はないと見る。譲るとは、弱さではなく責任である。自分の役目を終えたことを悟り、次が伸びる余白を残すことは、深い覚悟を要する。そこにこそ大和魂の真価がある。
大和魂とは、激しさや勇ましさだけを指す言葉ではない。自然の摂理を敬い、目立たぬところで次代を支える心である。自分が主役であり続けることを求めず、いずれ来る譲りの時を受け入れる静かな強さである。宮司は、その精神が日本人の暮らしや信仰の隅々に息づいてきたと感じている。
ゆずり葉は、神饌として神前に供えられてきた。神に捧げるとは、最も尊いものを差し出すことである。それは、命の循環を信じ、未来を託す心そのものを供えることにほかならない。正月にゆずり葉を目にするとき、日本人は無意識のうちに、その祈りを受け取っている。
子どもたちは、まだ小さな手で多くのものを受け取る。その重さにすぐ気づくことはないかもしれない。しかし、鳥のように歌い、花のように笑う日々の中で、やがて気づく時が来る。その時、再びゆずり葉の木の下に立ち、先人が何を譲ってくれたのかを思い出すだろう。
宮司は、日本の未来もまた、このゆずり葉の理に委ねられていると信じる。今を生きる世代が、何を次に手渡すのか。その問いから逃げず、誠実に生きることが、大和魂を未来へ繋ぐ唯一の道である。声を張り上げずとも、静かに根を張り、次の芽吹きを支える。その姿こそが、日本人の美しさであり、変わることのない精神のかたちである。
河井酔茗について
河井酔茗(かわい すいめい、1874 年 5 月 7 日 – 1965 年 1 月 17 日)は、日本の詩人であり明治・大正・昭和の詩壇を代表する人物の一人である。大阪府堺市に生まれ、若くして詩作に親しみ、雑誌『文庫』の記者として詩欄を担当することで多くの新人詩人を育てた。口語自由詩運動を推進し、日本詩人協会や大日本詩人協会の創立にも関わり、詩誌『詩人』の発行を通じて詩壇の発展に寄与した。詩集『無弦弓』『塔影』『花鎮抄』など多数の作品を残し、とりわけ詩『ゆずり葉』は子どもから大人まで広く親しまれている代表作である。
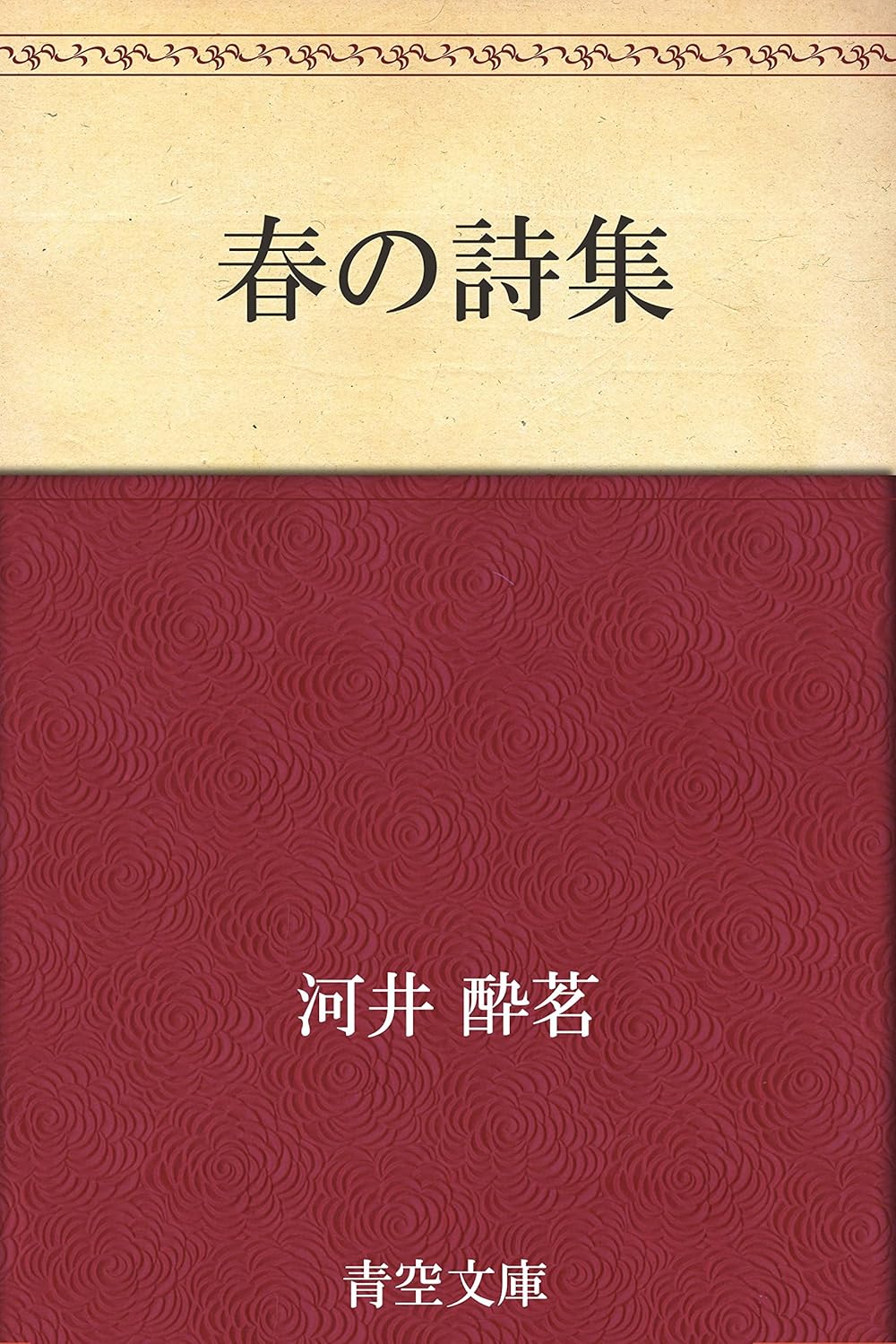
\ Amazon青空文庫「無料」 /