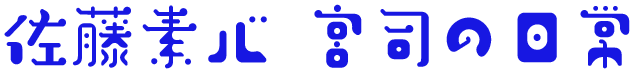門松に宿る日本人のこころ。歳神を迎え文化を未来へ手渡すために

正月を迎える日本の家々に立てられてきた門松は、単なる飾りではない。宮司は、門松という風習の奥に、日本人が古来より大切にしてきた精神の核心が宿っていると考えている。
門松は歳神さまをお迎えするための依りしろである。神は目に見えぬ存在でありながら、日本人はその訪れを具体的な形として表そうとしてきた。門松は、神が降りてこられる際の目印であり、同時に、清らかな世界とそうでないものとを分ける境でもあった。門に松が立つ家には神が迎えられ、穢れは近づけない。その感覚は、理屈を超えて日本人の暮らしに根づいてきたものである。
宮司が注目するのは、門松が自然と深く結びついている点である。松や竹はいずれも常緑であり、冬枯れの季節にも青々とした生命力を保つ。その姿に、人々は再生と永続を重ね合わせてきた。とりわけ松は、厳しい寒さの中でも変わらぬ色を保つことから、不変と長寿の象徴として尊ばれてきた。平安の昔、人々が松をめでたい木とし、やがて竹を添えるようになったのは、日本人の自然観そのものを映している。
かつては、各家が近くの山へ入り、門松用の松を自ら迎えに行った。「松迎え」と呼ばれるこの風習は、単なる準備ではない。正月という特別な時間を迎えるにあたり、心と暮らしを整える大切な節目であった。十二月十三日の事始めに始まり、決められた日を守りながら門松を立てる。二十九日を避け、三十一日を避けるのも、神を迎えるにあたり、軽んじた支度をしないという姿勢の表れである。
宮司は、こうした細やかな決まりごとにこそ、日本文化の品格が宿っていると感じている。便利さや効率を最優先にすれば、前日に慌ただしく飾っても問題はないかもしれない。しかし、日本人はあえてそれを良しとしなかった。見えない存在を迎えるからこそ、形を整え、時を選び、心を込める。その積み重ねが、正月という時間に重みを与えてきた。
近年、門松を見かける機会は確かに少なくなった。住宅事情や生活様式の変化もあり、本式の門松を立てることが難しい家庭が増えたのも事実である。だが宮司は、門松が姿を消していく風景に、日本人の感覚そのものが薄れていく危うさを感じている。門松が減るということは、神を迎える目印を立てるという意識が、日常から遠のいていることでもある。
その一方で、室内に飾るミニ門松が広まりつつあることに、宮司は静かな希望を見いだしている。形が変わっても、神を迎え、年の初めを寿ぐ心が残るならば、それは立派な継承である。玄関の脇、出窓の片隅、食卓の上に置かれた小さな門松にも、歳神さまを敬う気持ちは宿る。
正月飾りを松の内に取り払い、どんど焼きで天に返す風習もまた、日本人の精神性をよく表している。迎えるだけで終わらせず、感謝をもって見送る。年神さまが滞在する期間を意識し、区切りをつけることで、日常へと戻っていく。その循環が、日本の一年を形づくってきた。
宮司は、門松を通して伝えたいものは、過去への郷愁ではないと考えている。それは、日本人が何を大切にし、どのように生きてきたのかという指針そのものである。自然を敬い、見えないものに心を向け、節目を重んじる。その精神は、時代が変わっても色あせることはない。
令和の時代に生きる日本人が、門松を立てるかどうかは、それぞれの事情に委ねられる。しかし、正月を迎えるとき、なぜ門松が立てられてきたのかを思い起こすことには、大きな意味がある。門松は、神と人とをつなぐ目印であると同時に、日本人自身が自らの文化と向き合うための標でもある。
宮司は、新しい年の始まりにあたり、門松に込められたこの精神が、静かに、しかし確かに、次の世代へと受け継がれていくことを願っている。