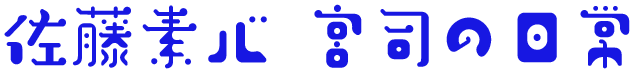鏡餅に託された祈り歳神を迎え、命をつなぐ日本の正月文化

正月を迎える日本の空間に、静かでありながら確かな存在感を放つものがある。それが鏡餅である。会社や店、そして各家庭の床の間や神棚に供えられた鏡餅は、新年の象徴であると同時に、日本人の精神文化そのものを映し出している。
鏡餅は、単なる餅ではない。丸く重ねられた餅の姿には、古来より神聖視されてきた「鏡」のかたちが重ねられている。鏡は神の御霊を映すものとされ、清らかで偽りのない心を象徴する存在であった。その鏡をかたどった餅を供えることで、歳神さまを迎え、共に新しい年を始めるという意識が育まれてきた。
宮司は、鏡餅の周囲に添えられる数々の縁起物に、日本人の願いの細やかさを見る。裏白は、表が緑で裏が白い葉を持つ。その姿に、後ろ暗いところのない清廉潔白な心が重ねられてきた。さらに、左右対になって伸びる葉脈は、夫婦が寄り添い、白髪になるまで共に生きる姿を表している。
譲り葉は、新しい葉が芽吹いてから古い葉が落ちる。その自然の循環に、家督を子へ、命を次代へと譲り渡していく願いが託された。家は個人のものではなく、連なり続ける命の場であるという感覚が、そこには息づいている。
昆布には「よろこぶ」という言葉遊びだけでなく、さらに深い意味が込められている。古くは広布と呼ばれ、喜びが広がることを願う縁起物であった。蝦夷の地で採れることから夷子布とも呼ばれ、恵比寿信仰とも結びついて福を招く象徴となった。また、子生の文字を当て、子宝と家の繁栄を願う心も重ねられてきた。
橙は、その名のとおり代々を意味する。冬に熟してもすぐには落ちず、何年も枝に残る果実の姿に、世代を超えて続く家族の姿が見立てられてきた。一つの木に複数年の実が残る様は、長寿と家運長久への祈りそのものである。
串柿には、さらに日本人らしい機知と温かさが込められている。両側に二つずつ、中に六つ並べられた干し柿は、ニコニコ中むつまじくという言葉を形にしたものだ。柿は嘉来に通じるめでたい果実であり、干し柿は渋柿が手をかけられ、床の間を飾る存在へと変わる。その姿には、修練を重ねることで人もまた磨かれていくという高い精神性が映し出されている。
宮司は、鏡餅の飾り方が地方や家ごとに異なる点にも、日本文化の豊かさを感じている。三宝に奉書紙や四方紅を敷き、紙垂を添える基本形がありながら、伊勢海老や勝栗、黒豆、するめなど、土地の暮らしと信仰に根ざした縁起物が加えられてきた。正解が一つではないからこそ、それぞれの家の歴史と祈りが息づく。
餅つきが年の瀬に行われてきたのも意味深い。二十八日や二十九日に、家族や地域が力を合わせて餅をつく。そこには、新しい年を迎える準備を共同で行うという大切な時間があった。便利な時代となり、その光景は少なくなったが、餅を供えるという心まで失われてよいはずがない。
鏡餅は、食べるためだけに供えられるものではない。歳神さまを迎え、正月という特別な時間を共に過ごすための依りしろである。松の内が明け、鏡開きの日に餅をいただくのは、神の力を分かち受け、一年を健やかに過ごすための願いが込められている。
宮司は、鏡餅の文化が伝えてきたものは、過去の風習ではなく、未来に必要な心の在り方だと考えている。清らかさを尊び、命のつながりを意識し、家族や社会の調和を願う。その精神は、時代がどれほど変わっても、日本人の根に流れ続けるものである。
新しい年の始まりに、鏡餅を前に立ち止まり、その意味に思いを巡らせる。そのひとときこそが、日本の文化と伝統を未来へと手渡す、静かで確かな一歩となる。