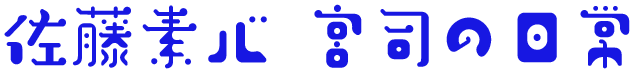安倍元総理の魂とともに宇治橋を渡る高市総理

伊勢の杜に足を運ぶたび、日本人がどこから来て、どこへ向かおうとしてきたのかを静かに問い返される思いがする。五十鈴川の清流に架かる宇治橋は、単なる参道の入り口ではない。日常と聖域を分かつ境であり、過去と現在、そして未来を結ぶ象徴である。
高市早苗首相が安倍晋三元首相の写真を胸に抱き、宇治橋を渡られた姿は、多くの日本人の心に深い余韻を残したことだろう。写真というかたちであっても、ともに橋を渡り、ともに神前へ進む。その姿に込められていたのは、個人の追憶を超えた、日本の精神文化そのものへの敬意である。
伊勢神宮は、何かを願いに来る場所である以前に、感謝を捧げる場である。国家の安寧、国民の暮らし、先人から受け継いだ恵み。そのすべてに対し、言葉少なに頭を垂れる。その積み重ねが、日本という国の背骨を形づくってきた。
安倍元首相が在任中、年頭に伊勢へ足を運び続けたことは、政治的な慣例ではなく、国家観の表れであったと受け止めている。国の舵取りを担う立場にある者が、年の始めに皇祖の御前に立ち、私心を離れて国を思う。その姿勢こそが、政治を単なる権力運用ではなく、歴史と倫理に根ざした責務へと引き上げてきた。
伊勢志摩サミットの折、世界の首脳が伊勢の地を訪れた光景も忘れがたい。異なる文明、異なる価値観を背負った人々が、言葉を超えて日本の静謐に触れた。その背景には、自然とともに生き、目に見えぬものを敬ってきた日本人の精神がある。声高に主張せずとも、佇まいそのものが語る文化。それが伊勢であり、日本である。
宮司は、今回の参拝において示された「もう一度、連れて来てあげたかった」という言葉に、日本人特有の情の深さを見る。亡き人を完全に過去へと押しやるのではなく、今なおともに在る存在として敬う心。その感覚は、祖霊を祀り、先祖と語りながら生きてきたこの国の精神土壌から生まれている。
日本の伝統文化は、博物館に収められるためにあるのではない。日々の暮らしの中で思い起こされ、折に触れて身体を通して確かめられることで、初めて未来へと手渡されていく。伊勢への参拝もまた、その連なりの一部である。
変化の激しい時代にあっても、変えてはならぬ軸がある。自然への畏敬、先人への感謝、そして次代への責任。その軸を見失わぬために、日本人は伊勢へ向かう。足を運べぬ者であっても、心の中に伊勢を持つことはできる。
宮司は、今回の出来事が、一過性の美談として消費されることを望まない。写真を携えて橋を渡る姿に重ねるべきは、それぞれが自らの立場で、何を未来に残そうとしているのかという問いである。
伊勢の神域は、いつの世も変わらずそこに在り続ける。しかし、そこから何を受け取り、どう生かすかは、今を生きる日本人一人ひとりに委ねられている。精神を磨き、伝統を次代へ繋ぐ道は、遠くにあるのではない。感謝を忘れぬ心と、静かに頭を垂れるその一歩から、すでに始まっている。