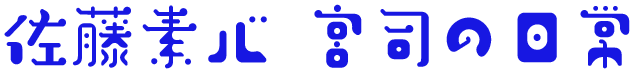神籬という祈り。自然とともに生きてきた日本人の原点

宮司は、「神籬」(ひもろぎ)という言葉に、日本人の信仰の原点を見る。社殿も彫刻も持たぬ時代、人々は山に、岩に、木に、海に、目には見えぬ気配を感じ取り、そこに神の依り代を見出してきた。神籬とは、神を閉じ込める場所ではなく、神を迎えるために整えられた、きわめて慎ましく、しかも厳粛な場である。
神籬の齋の庭に映える南天の赤は、自然がそのまま神事となる日本の美意識を象徴している。人工の飾りではなく、季節の移ろいの中で実る一粒の赤に、清浄と祈りが宿る。宮司は、ここに日本人の精神の研ぎ澄まされた姿を見る。余計なものを足さず、自然そのものに心を澄ませる態度である。
神籬の語義には諸説があるが、いずれも木を中心に神を迎える思想に帰着する。榮樹を立て、そこを神の御室とする考え、生きた森そのものを神の憑り坐す場とする捉え方、檜の葉をもって仮の神室を設ける意。いずれも共通しているのは、神は人が造った器にではなく、清められた自然に宿るという感覚である。
万葉の時代から、人々は神籬を立て、身を慎み、心を整えて神を迎えてきた。そこには、神を呼びつけるという発想はない。人が場を清め、己を正し、神が来臨するのを静かに待つ。その姿勢は、現代において失われつつある謙虚さを思い起こさせる。
やがて社殿が建てられ、祭祀の形は変わった。しかし、神籬の精神は消えていない。玉垣の内に常盤木を立て、そこを神の坐すところとする古式の神社に、その名残は今も息づいている。地鎮祭に用いられる神籬もまた、土地に神を迎え、これから始まる営みが自然と調_toggleし得るよう祈る行いである。
宮司は、神籬に立つ一本の木を前にするとき、日本人が本来持っていた大和魂の姿を思う。それは、自然を征服する心ではなく、自然と共に在ろうとする心である。力で押し通すのではなく、理を敬い、目に見えぬものに畏れを抱く感性である。この感性こそが、日本の文化を静かに支えてきた。
大和魂とは、剣や声の大きさに宿るものではない。神籬の前で一歩身を引き、息を整え、己を省みるところに芽生える。神霊が天下る木の下に立ち、自分が自然の循環の中の一部であることを知るとき、人は驕りを捨て、責任を自覚する。その積み重ねが、世代を超えて受け継がれてきた。
現代社会は、効率や即時性を重んじ、目に見える成果ばかりを求めがちである。しかし宮司は、神籬の思想が示すように、見えぬものを敬う心なくして、真の安定や未来は築けないと考える。自然を単なる資源と見なす態度は、やがて人の心をも荒廃させる。
神籬は、過去の遺物ではない。今を生きる日本人が、再び立ち返るべき精神の座標である。南天の赤に季節を感じ、常盤木の緑に永遠を思い、静かに頭を垂れる。その一瞬に、日本人の魂は研ぎ澄まされる。
宮司は願う。神籬の精神が、形としてではなく心として、次の世代へと譲られていくことを。自然を敬い、見えぬものを恐れ、己を慎む心が失われぬ限り、大和魂は決して枯れることはない。その魂が未来へ繋がるとき、日本は再び静かな強さを世界に示すだろう。
神籬(ひもろぎ)について
神籬とは、神さまをお迎えするために設けられる清浄な場所である。社殿が建てられる以前、日本人は山や森、巨木など自然そのものに神が宿ると考え、木を立て注連縄で囲い神籬とした。人が神を迎えるために場と心を整える、日本古来の信仰のかたちである。