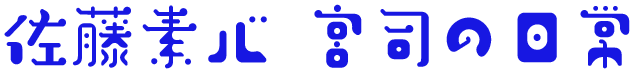桃太郎から始まる日本再生。子供に手渡すべき強さと優しさ

日本再生の道をどこから歩み直すのかと問われるなら、宮司は迷わず「物語」からだと答える。とりわけ桃太郎である。桃太郎は単なる昔話ではない。日本人が長い年月をかけて磨き上げてきた、正しさと勇気と優しさの結晶であり、子供に伝えるべき精神の原型である。
戦後の学校教育は、知識を与える一方で、人が生きるために本来備えるべき力を削いできた。善と悪を見分ける感覚、理不尽に立ち向かう勇気、弱き者に寄り添う心、それらが意識的に曖昧にされてきた結果、強さを語れば危険、正義を語れば排外と決めつける風潮が広がった。宮司には、その行き着く先が子供たちから背骨を抜くことにしか見えない。
桃太郎は、人を害し、子供をさらい、村を荒らす鬼の存在を知り、立ち上がる。ここには理由なき攻撃はない。守るべきものがあり、見過ごせぬ現実があり、そのために旅立つ決意がある。これを侵略と呼ぶなら、正義という言葉そのものが成り立たなくなる。
道中で出会う犬、猿、雉は、上下関係で結ばれた存在ではない。それぞれの特性を認め合い、力を合わせる仲間である。犬の仁義、猿の知恵、雉の勇気が一つに結ばれたとき、困難に立ち向かう力が生まれる。これは共同体の理想であり、日本社会が本来大切にしてきた姿である。
桃太郎の物語が各地に根を張り、地名や社として今も残るのは偶然ではない。古事記に記される桃の霊力、災いを退け人を救う象徴としての桃は、日本人の精神史の深層に息づいている。物語と神話と土地の記憶が重なり合い、子供を守る神として祀られてきた事実は、桃太郎が単なる創作ではないことを物語っている。
宮司は、桃太郎が好きである。強いからだけではない。優しさがあり、勇気があり、決して独りで戦わないからである。好きな人に好きだと言えない臆病さを美徳とせず、力を持ちながらも思いやりを失わない。その姿こそ、日本男子の理想像であり、男女を問わず人としての目標でもある。
近年、桃太郎を一面的に切り取り、侵略の物語と断じる教育が実際に存在した。教科書に掲載され、検定を通り、疑問を抱かぬまま子供たちに与えられた。これは多様な解釈の一つという問題ではない。物語の文脈を断ち切り、日本人自身の文化を否定する思想を、公の教育に持ち込んだことが問題なのである。
子供たちは理屈より先に物語から学ぶ。善を善として描き、悪を悪として描く物語があるからこそ、心の軸が育つ。すべてを相対化し、どちらも同じだと教える教育は、判断する力を奪う。宮司は、それを教育とは呼ばない。
日本のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんに伝えたい。桃太郎の話を語ってほしい。絵本でも、言葉だけでもよい。猿と犬と雉を連れて鬼退治に向かう話を、声に出して伝えてほしい。その時間こそが、次の世代に大和魂を手渡す営みである。
日本の未来は、制度や数字だけで再生するものではない。物語を失った民族は、やがて自分が何者かを見失う。桃太郎は、日本人が日本人であるための羅針盤である。明るく、強く、勇気ある子供を育てるために、今こそ原点に立ち返る時である。
桃太郎のモデルは天皇のご子息
桃太郎のモデルとされる人物は、第7代孝霊天皇の第三皇子である吉備津彦命(きびつひこのみこと)である。岡山県に伝わる「温羅(うら)伝説」が物語の原型であり、吉備の地を荒らしていた温羅という鬼を、朝廷の命を受けた吉備津彦命が討伐した歴史的な伝承に基づいている。
お供のイヌ・サル・キジについても、吉備津彦命に仕えた実在の家臣や部族がモデルとされ、それぞれ犬養健(いぬかいたける)、楽々森彦(ささもりひこ)、留玉臣(とめたまおみ)という名で語り継がれている。元来は皇子による地方平定の記録であったが、室町時代から江戸時代にかけて、魔除けの象徴である「桃」の要素が加わり、教育的なおとぎ話として現在の形に定着したのである。