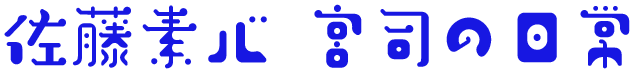魂のふるさとに立ち返る

宮司は、深い悲しみや絶望に触れる時こそ、人の精神が本来のふるさとに還る瞬間だと考える。誰もが人生の途上で「神などいない」と言い切りたくなるほどの試練を味わう。最愛の人を失い、大切な夢を砕かれ、命の意味さえ見失う時がある。しかし、その言葉の裏には、計り知れないほど純粋な心の叫びが隠されている。
宮司は、その痛みを抱きしめ、代わりに涙を流す存在でありたいと思う。安倍神像神社に参詣に来られた方に、苦しみを「長野に捨てて帰りなさい」と伝えるのは、悲しみを否定するのではなく、自然の懐に委ねて心を休めてほしいからだ。人は弱いからこそ傷つき、純粋だからこそ堕ち込む。だからこそ、肩の力を抜いてもよいのだと伝えたい。
恐怖や不安に震える時も、宮司はその感情を抱きしめる。逃げても追ってくる心の影を、自然の懐に託すことで、初めて静けさが訪れる。人の心は決して強靭ではない。軋み、揺れ、壊れそうになるものだ。それでも「生かされている」という感謝の思いが芽生えれば、また明るい光を受けて歩き出せる。
宮司は、こうした祈りを通じて、日本人が古来より大切にしてきた精神を呼び覚まそうとしている。それは、天地の恵みに感謝し、万物の命に敬意を払う心である。自然の循環に身を委ね、自らもその一部として生かされていることを受け容れる時、人は「清くやさしい心」に立ち返ることができる。
「今日という命は限りなき恩」と感謝し、ほほえむ。その姿勢こそ、日本人の精神の根幹であり、魂のふるさとに帰る道である。