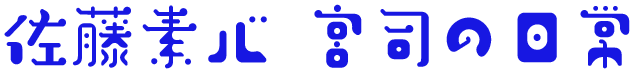明徳を曇らせぬために、何を拠り所として学ぶのか
宮司が論語公開講座の勉強会に参加したのは、今から二十年ほど前のことである。当時は今よりは少し若く、学びに対する焦がれるような情熱と、同時に拭えない不安が胸の内に交錯していた。大きな期待を抱き足を運んだが、講話の内容は心に響かなかった。難解だから理解できなかったのではない。語られる言葉が、人生の現場から切り離され、どこか宙に浮いたまま届くように思えた。学問の形式が前面に出て、生きた人間としての息づかいが欠けていた。
その違和感を抱えたまま帰路につき、本屋で伊與田覺先生の『大学』を手に取った。車内で読み始めると、言葉が急に温度を帯び始めた。古典の香気と共に、人間を見つめ続けた者だけが発する静かな確かさが伝わってきた。当時はその理由を言語化できなかったが、年月を経た今ならはっきりと言える。学問として古典を扱う者と、人生を通して古典を生きる者との違いである。
加地伸行氏の講話に感じた空虚さは、古典を対象として扱う「知的作業」に偏っていたことから生じたものである。一方、伊與田先生の言葉は、古典が人をどう鍛え、どう正し、どう導くかを「体験」として語っていた。文字の奥にある人間の魂がそのまま流れ込んでくるような迫力があった。
平成二十八年に伊與田先生が亡くなられたとき、宮司は深い孤独を覚えた。しかしその感情は、先生の著作を読み返すたびに変化した。亡くなったという喪失だけが残ったのではない。先生が残した言葉が生きて呼吸し続けることを実感するようになった。古典を通じて人格を磨き続けた者の言葉は、時間を超えて生きる。その事実が、宮司にとって揺るぎない支えになっていった。
特に「孝」を語る際の解釈の違いは顕著である。加地氏は孝の本質を諫言に求めた。しかし孝とは、まず深い敬と慈しみから発するものであり、諫めはその延長にすぎない。諫言だけを孝としてしまえば、敬を失った直情の言葉も正義になってしまう。中江藤樹先生も安岡正篤師父も、そのような孝の矮小化を認めなかったはずである。ここに古典を「覚える学び」と「生きる学び」の分岐がある。
宮司は二十年という歳月の間で、多くの現実を経験し、人と向き合い、神職としての責務を果たしながら、論語や大学に記された教えの重みを身をもって感じるようになった。加齢ではなく、経験が教える理解である。古典の価値は、年齢ではなく、生活の汗とともに滲み出る。だからこそ、人生を歩むほどに、伊與田先生の言葉はより深く心に染み込んでいく。
宮司が改めて痛感するのは、古典を学ぶ目的は知識の増加ではなく、明徳を曇らせぬためであるという一点である。己を修めるとは、誰かに見せるための修行ではない。期待もせず、淡々と積む。人知れず積んだものが、ある日、風格として表に現れる。伊與田先生が説いたこの姿勢は、宮司の中で揺らぐことのない灯となった。
影響力のある立場に立つ者ほど、象牙の塔に閉じこもる危険が高まる。知識が増えると、自分が何を失っているかに気づきにくくなる。だからこそ、古典は不断の鏡でなければならない。古典を自ら照らす道具として使うのではなく、古典に自分が照らされることで初めて心の歪みが正される。
日本の社会が精神的に不安定になっている背景には、この「照らされる姿勢」を失っていることがあるのではないか。古典は情報ではない。生き方の根を整える道である。道徳と経済を一致させた松下幸之助の成功も、独特の知恵ではなく、古典の素読と実践に支えられた生き方であった。根が整えば、枝葉も伸びる。日本人が本来持っていた力は、そこにあったはずである。
宮司は思う。日本の再生は、誰かが大きな旗を振ることで起こるのではない。一人一人が自らの心を修め、周囲に静かな光を広げていくことで、自然に形づくられていく。これが大学の「修己治人」の精神であり、日本が長く育んできた倫理観である。
伊與田覺先生の言葉は今も生きている。先生の手から古典の火を受け取った者は、その火を自らの生き方で次代へ渡さなければならない。明徳を曇らせぬために、古典を読み続け、生活の中に落とし込み、言葉ではなく行動で示す生き方を貫いていきたい。
宮司にとって古典は、過去の遺物ではない。未来へ向けて心を整える道である。二十年前の虚しさも、今となっては大きな気づきへの入口であった。学びとは、年月によって磨かれ、経験によって骨格が生まれる。これからも静かに、しかし確かに、修己治人の学を歩んでいく。
\ [PR]Amazon /