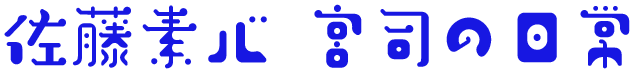一つの甘味に宿る日本の心。それが“あんぱん”

人の一生には、ふとした拍子に胸の奥から立ち上がってくる味の記憶がある。豪勢でも華やかでもない、けれど決して消えない味である。アンパンは、そのような記憶の底に、今も静かに残り続けている。
幼いころ、叱られた後に差し出されたのは、決まって一つのアンパンであった。涙を流しながら、無言でかじる。その姿を見つめながら、「アンパン…おいしいか、しょっぱいか」と、いつも同じ言葉が静かに投げかけられた。声を荒げて追い打ちをかけることはなかった。怒りの後に残されたのは、甘さと温もりであった。そこには、言葉よりも深い教えがあった。叱るとは突き放すことではなく、立ち上がらせることであるという、日本人の古い知恵が、確かに息づいていた。
宮司は、アンパンという素朴な食べ物の中に、日本人の情と節とが重なり合って宿っているのを感じずにはいられない。甘さとは、甘やかしではない。涙を受け止め、もう一度前を向かせるための力である。その力は、何も語らぬ一口の中に、黙って込められていた。
成長してからも、なぜかアンパンが好きだとは言えなかった。どこか子供のままのように見られそうで、照れのようなものが先に立つ。喉から手が出るほど食べたいときでさえ、心の奥にしまい込む癖は変わらない。しかし、無性に懐かしくなる瞬間がある。そのたびに、あの甘さと、あの問いかけが、胸の奥でそっとよみがえる。
田舎の学校の近くの小さなパン屋。クラブ活動で空腹を抱えた帰り道、アンパンで満たされた一日の終わり。あの甘味は、ただの菓子ではなかった。汗と疲れと、明日への力をつなぐ糧であった。
アンパンは、日本で生まれ、日本人の口に合わせて育てられてきた、日本独自のパンである。異国のパンと、日本古来の餡が、互いを拒まず、溶け合い、調和のかたちとなった。拒まず、流されず、己の形に整える。その姿勢そのものが、日本人の精神の歩みであった。
酒種で焼き上げられる銀座のあんパンには、和菓子とパンの境が静かにほどける趣がある。発酵という目に見えぬ営みを信じ、急がず、誤魔化さず、時を待つ。そのものづくりの姿に、日本人の生き方がそのまま重なって見える。
地方に根づいたあんぱんもまた、土地と人の記憶を宿している。労苦の中で人の命を支え、疲れた体に力を与え、黙って寄り添ってきた甘味。そこには、支え合いの心が、甘さとなって残っている。
アンパンの温もりは、砂糖の働きだけではない。叱る者の葛藤、叱られる者の涙、それでも差し出された一つの甘味に込められた赦しと願い。そうした無言の心の往復こそが、日本人の和の原風景であった。
和とは、争いのないことではない。ぶつかり合ったその後に、なお相手を見捨てぬ覚悟があるかどうかである。アンパンは、その覚悟を、何も語らずに人の手へ渡してきた。
日本人の精神は、声高な言葉の中では育たない。日々の所作の中で、静かに磨かれていく。涙をぬぐいながら一口をかじる、その姿にこそ、民族の品が映る。強さとは威圧ではなく、折れぬ心である。優しさとは迎合ではなく、導く力である。
甘さを照れ、涙を隠し、それでも温もりは手放さない。そうした不器用な生き方の中に、日本人が守り続けてきた誇りがある。アンパンは、その誇りを、今も変わらぬ丸い姿で、人から人へと手渡し続けている。
派手ではない。だが、確かに強い。甘さの奥に、苦さと涙と忍耐を抱いた、あの一口のように。