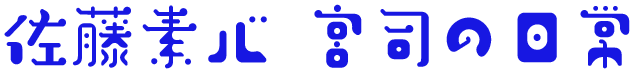彌榮の祈りが問いかけるもの。先人の犠牲と大和魂の真実

宮司は、日本の国を守るために命を捧げた先人に対し、まず深い敬意と畏敬の念をもって頭を垂れる。彌榮、彌榮、彌榮。その言葉は、賛美や陶酔のためではなく、永久に安らかであれという祈りとして捧げられるものである。そこにあるのは、戦争を美化する姿勢ではない。歴史の中で確かに生き、悩み、決断し、命を落とした人々の存在を、事実として正面から受け止めようとする態度である。
宮司は、戦争を賛美することと、戦争の真実を見つめることは、決して同一ではないと考える。何が正しく、何が誤っていたのかを見極めるためには、感情的な断罪でも、思考停止した肯定でもなく、冷静で誠実な眼差しが必要である。その作業を放棄したとき、歴史は教訓を失い、民族の精神は摩耗していく。
戦後日本の教育現場では、先の大戦は一方的な侵略であり、悪であり、恥であったと断じる教えが繰り返された。宮司は、その言葉を疑う余地のない真実として受け取るよう求められてきた世代の存在を知っている。国を思う心は危険視され、国旗や国歌は忌避され、日本人であることそのものが、どこか後ろめたいものとして扱われた時代があった。
しかし、学びを重ね、史料に触れ、世界史の構造を知るにつれ、単純な善悪二元論では語れない現実が浮かび上がってくる。宮司は、当時の国際情勢において、アジアが欧米列強の植民地支配の波に呑み込まれつつあった事実を直視する。理想的であったかどうかは別として、日本がその渦中で立ち上がった背景には、同じアジアの民が置かれていた過酷な状況があったことも否定できない。
宮司は、そこに無謀さがなかったとは言わない。多くの判断に誤りがあり、多大な犠牲が生じたことも事実である。それでも、すべてを侵略という一語で切り捨て、先人の動機や苦悩を顧みない態度は、真実から目を背けることに等しい。歴史とは、都合のよい部分だけを拾い上げるものではなく、光と影の両方を引き受ける覚悟の上に成り立つ。
宮司は、思想や主義の名の下に、個々の日本人の思いや葛藤が踏みにじられてきた戦後の風潮に、強い危惧を覚える。特定の思想に立脚した歴史観が、唯一の正解として語られるとき、人は考える力を奪われる。考えない国民は、いずれ自らの足で立つことができなくなる。
大和魂とは、声高な主張でも、他者を攻撃する姿勢でもない。宮司は、大和魂を、事実を直視し、責任を引き受け、なお誇りを失わない精神のあり方だと捉える。先人の選択を全肯定する必要はない。しかし、命を懸けて国と時代に向き合った人々の存在を否定する権利は、誰にもない。
宮司は、未来の日本人が、自国の歴史を自分の言葉で語れるようになることを願う。他国に迎合するためでも、過去を正当化するためでもなく、真実を知り、引き受け、その上で次の時代を築くためにである。大和魂は、過去に閉じ込められるものではない。問い続ける姿勢の中でこそ、磨かれ、受け継がれていく。
先人に対する恭しい拝礼は、過去への別れではなく、未来への誓いである。宮司はそう確信している。彌榮、彌榮、彌榮。その祈りとともに、日本人の精神が再び静かに、しかし確かに立ち上がることを信じてやまない。