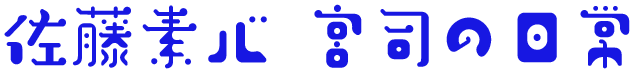なぜ日本人は「損得」で生きるようになったのか

宮司は、戦後の日本社会に広がった価値観の変質に、長年強い違和感を覚えてきた。その象徴が「損得」という言葉である。何かをなす理由を問えば、どれほどの見返りがあるのか、時間や労力に対して得るものは何かと即座に計算が始まる。人を助けることですら、条件付きで語られる時代となった。
東日本大震災後、福島での支援について「結構お金がもらえるらしい」という言葉を耳にしたとき、宮司は言葉を失った。困窮する人々のために力を尽くすことが、報酬の多寡で語られる現実に、時代の深い歪みを感じたのである。本来、ボランティアとは無償で困った人に寄り添い、見返りを求めず汗を流す心の在り方であったはずだ。
募金活動の場で集められた浄財から賃金が支払われているという話を聞いたとき、宮司はそれを「ボランティア」と呼ぶことに強い疑問を抱いた。それは労働の対価としての仕事であり、アルバイトと何が違うのかと考えざるを得なかった。無償で動く若者はいないと言われたとき、宮司は社会全体が何か大切なものを失ってしまったのではないかと感じた。
戦後日本は、社会や国のために尽くす心を育てるよりも、個人の利益や効率を優先する考え方を教え込んできたのではないか。宮司は、教育の現場で「何のために生きるのか」「誰のために力を使うのか」という根本が語られなくなったことを憂えている。
その思いを強くした出来事があった。東京から来た中学生たちに「にのみやそんとく」を知っているかと問いかけたときのことである。漢字で書いてみるよう促すと、多くの生徒が「二宮損得」と記した。正しく「二宮尊徳」と書けたのは、わずか三名であった。宮司は、戦後教育が教えるべき精神を教えず、試験に出る知識だけを教えてきた結果を、そこに見た。
二宮尊徳翁は、損得で生きた人物ではない。尊徳翁の生涯は、徹底して人々の暮らしを立て直すことに捧げられていた。幼くして家を失い、両親を亡くし、艱難辛苦の中で働き学び続けた尊徳翁は、自らの境遇を嘆くことなく、努力と節度によって道を切り開いた。その精神は、他者のために力を尽くすことが、結果として社会全体を潤すという確信に支えられていた。
桜町領の復興にあたり、尊徳翁は私財を投じ、村人と共に汗を流した。反発や妨害を受けても志を曲げず、必要とあらば身を引く覚悟すら示した。その姿に人々は心を動かされ、やがて信頼と協力が生まれ、荒れ果てた土地は再び息を吹き返した。宮司は、ここに日本人が本来持っていた公共への責任感と、未来を見据える精神を見る。
尊徳翁の教えは、報徳という言葉に集約される。受けた恩を社会に返し、次の世代へとつないでいく思想である。そこには即時の見返りはない。しかし、長い時間をかけて共同体を支える確かな力があった。宮司は、現代日本がこの思想を忘れつつあることに、深い危機感を抱いている。
損得だけで物事を判断する社会は、短期的には合理的に見えるかもしれない。しかし、見返りを求めぬ努力や、名も残らぬ献身が失われたとき、社会の根は確実に枯れていく。宮司は、大和魂とは、声高な主張でも、他者を押しのける力でもなく、静かに、黙々と、誰かのために力を尽くす心だと考える。
二宮尊徳翁を知らぬまま大人になる若者が増えることは、日本人の精神的な背骨が失われていくことに等しい。宮司は、過去を美化するためではなく、未来を支えるために、先人の生き方を学び直す必要があると訴える。
日本人の精神は、損得を超えたところでこそ研ぎ澄まされる。見返りを求めず、次代のために尽くす心が、大和魂の本質である。宮司は、その精神を再び呼び覚まし、未来へと手渡すことが、今を生きる日本人に課された責務であると確信している。