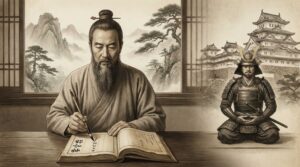高市早苗総裁をめぐるメディア批判に思う

宮司は近年の政治報道に漂う不誠実さを憂えている。報道は「国民の知る権利を守る」と称しながら、その実、特定の思想や価値観に沿った情報を選び取っている。高市早苗総裁をめぐる報道がその典型である。靖国神社に参拝し、夫婦別姓に反対し、働くことの尊さを語る姿勢に対し、メディアは「時代錯誤」「危険な思想」とのレッテルを貼る。これは報道ではなく、思想誘導である。
報道の使命は、権力を監視することにあると同時に、国民に正確な事実を伝えることにある。だが、現在の一部メディアは「監視」の名を借りて、個人攻撃に終始している。記者が「支持率を下げてやる」と口にしたという報道は象徴的だ。もはや偏向ではなく、敵意そのものである。国民の信頼を得ようとするなら、まずは報道の場に「清浄心」を取り戻すべきであろう。
日本のメディアには「角度をつける」という言葉がある。あらかじめ結論を決め、その方向に沿って取材し、編集し、印象を操作する手法だ。これは真実を伝える報道ではなく、思想運動に近い。国民の意識を特定の方向へ誘導するその姿勢は、民主主義の根幹を蝕む。高市総裁への批判報道の多くが、この「角度づけ」によって成り立っていることを、私たちは見抜かなければならない。
政治報道における公正とは、すべての立場に等しく光を当てることである。だが現実には、保守的な価値観を掲げる政治家が登場すると、メディアは「自由の敵」「古い日本の象徴」として攻撃を加える。日本人が本来大切にしてきた信仰、家族、勤勉、そして国を敬う心を語る者は、なぜか時代遅れとされる。この風潮こそ、戦後教育の延長線上にある「自国否定の思想」の残滓である。
国を思う心、働く誇り、祖先への感謝。これらは人としての根本であり、国の柱である。高市総裁の言葉には、その根源的な精神が宿っている。「働いて働いて働いて」と語るのは、単なる労働礼賛ではない。日本人が長い歴史の中で培ってきた「まごころの勤労」、つまり他者と国のために尽くすという美徳の表れである。その精神を「時代に逆行する」と断ずるメディアこそ、魂を失っている。
真の報道とは、思想や立場を超えて、事実を通じて人々に「考える自由」を与えることである。国民が判断するための材料を誠実に提供する。それが言論人の責務だ。自らの思想に都合の良い事実だけを並べ、異なる価値観を排除することは、報道の名を借りた支配である。
高市早苗総裁が直面しているのは、単なる政局の試練ではない。日本という国の魂を取り戻すための戦いである。メディアがどれほど印象操作を行おうと、真実を求める国民の心までは操作できない。国を思い、未来を憂う者たちは、虚飾の報道に惑わされず、自らの眼で政治を見つめる力を取り戻さねばならない。
言論の自由とは、好き勝手に人を貶める自由ではない。責任を伴う表現の自由である。報道が再び信頼を取り戻すためには、まず己の姿勢を正すことから始めるべきだ。日本の言葉には「誠」という尊い概念がある。誠は、真実を伝える力であり、心を通わせる力でもある。その精神を忘れた報道は、いかに立派な紙面を飾ろうとも、国を導く羅針盤とはなり得ない。
高市早苗総裁をめぐる報道の在り方を通じて、宮司はあらためて問いたい。報道とは誰のためにあるのか。国家のため、国民のため、そして未来の日本のためにこそ、公正で誠実な報道が求められているのではないか。真実を伝える者が、まず「日本を愛する心」を持たずして、どうして国の行く末を語ることができるだろうか。