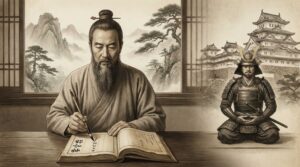成長する日本へ。高市内閣と片山財務相の姿に学ぶもの

高市内閣の船出は、国民の期待を大きく上回るものとなった。支持率64%という数字は、単なる新鮮さや話題性だけでは説明できない。そこには、誠実さと覚悟を見極める国民の感性が確かに働いている。政治に求められているのは、派手な言葉ではなく、静かな信念と責任感である。その象徴が高市早苗首相の姿にあると感じる。女性として初めて日本の頂点に立ったという事実よりも、国家を背負う覚悟をもってその地位に臨む姿に、人々は心を動かされたのだろう。
一方、片山さつき財務相が就任会見で放った「帳尻を合わせることだけが目的ではない」という言葉は、単なる財政論を超えて、国の在り方そのものに通じる深い示唆を含んでいる。数字を整えることは手段であって、目的ではない。国家財政の本来の使命は、未来を拓くために必要な投資を恐れず、国民が安心して生きられる環境を整えることにある。片山氏が「恐竜にはならない」と語ったのは、かつての厳しい上司としての一面を自覚しつつ、恐怖で部下を動かすような古い指導者にはならないという決意の表れである。人を叱咤するより、共に考え、共に責任を担う姿勢を選ぶ。そこには、指導とは支配ではなく導きであるという信念がにじんでいる。
政治とは、本来「正しいことを正しく行う」営みである。だが、時代が進むにつれて、派閥や利権、人気取りといった雑音が増し、その本質が見えにくくなってきた。高市内閣が国民から歓迎されている理由の一つは、こうした旧弊を打ち破ろうとする真摯な姿勢にある。とくに、自民党と維新の連立を評価する声が多いのは、理念や派閥の壁を越えて「現実を動かす政治」を志向する姿勢が見えているからだろう。公明党の離脱を肯定的に捉える世論も、国民が「自立した政治」を求めている表れに他ならない。
日本人の精神の根底には、「和して同ぜず」という言葉がある。調和を重んじながらも、信念を曲げない。高市首相も片山財務相も、まさにその精神を体現している。周囲と協調しながらも、譲ってはならない一線を持ち、国家と国民のために決断する。その姿は、明治の先人たちが抱いた「国を富ませ、民を安んじる」という理念の現代的な再現でもある。
宮司は、この二人の姿に日本の再生の兆しを見る。国を思い、民を思う政治が再び動き出したとき、そこには自然と希望の灯がともる。政治家の言葉に誠実さが戻り、行動に品格が宿るとき、国は必ず立ち直る。日本は、まだまだ強く、そして美しい国である。政治の刷新は、同時に国民一人ひとりの精神の刷新でもある。高市内閣の出発は、新しい時代の日本人の在り方を問い直す鏡である。国民が真に成長する国を選び取れるかどうか、それが今、試されている。