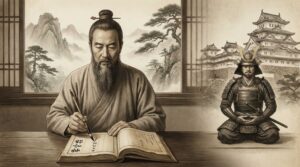祖国を想う祈り。高市早苗総理の拉致被害者への決意に寄せて

宮司は、官邸で拉致被害者御家族と向き合う高市早苗総理の姿に、深い感慨を覚えた。政治の世界には、言葉が軽く流されることが多い。しかし、この日ばかりは違った。高市総理の一言一言に、国家を背負う者としての責任と、母としての慈しみが同居していた。
拉致問題とは、単なる外交課題ではない。人の命を奪い、家族の絆を引き裂く暴挙であり、国家主権への明白な侵害である。1970年代から80年代にかけて連れ去られた多くの拉致被害者は、いまだ祖国に帰ることができずにいる。2002年に5名の被害者が帰国してから、すでに二十三年が過ぎた。その後、新たな帰国は一人も実現していない。横田早紀江さんをはじめとする御家族が流した涙は、個人の悲しみを超え、民族の祈りそのものである。
宮司は思う。日本という国は、血の通った共同体である。誰かが拉致され、苦しむなら、それは国民全体の痛みである。だからこそ、総理の言葉の中に「国家主権」と「命の尊厳」を同時に掲げたことに、深い意味がある。国とは領土でも制度でもなく、そこに生きる人々の尊厳を守る決意そのものだ。
高市総理が語った「金正恩委員長との首脳会談に臨む覚悟」という一節に、宮司は信念の重さを見た。対話は屈服ではなく、勇気の形である。危険を恐れず、あらゆるチャンスを逃さない姿勢に、日本の未来を託したいと思う。過去の政権が築いた外交ルートを踏まえつつも、自らの責任で突破口を開こうとする姿勢は、まさに「令和の政治家像」を示している。
日本は今、経済の停滞、少子化、国際秩序の揺らぎという難局のただ中にある。しかし、いかなる時も、政治の原点は「人を守ること」にある。拉致問題の解決を求める家族の声に、真っすぐに応えようとする総理の姿勢は、政治の本義を思い出させてくれる。
宮司は、かつて古事記に記された「国を鎮め、民を安んずる」という言葉を思い出す。国家とは、遠い理念ではなく、日々の暮らしの延長にある。母が子を思うように、為政者が民を思う国であってこそ、そこに真の独立が宿る。
高市早苗総理の前に集った御家族の涙は、絶望ではなく希望の証である。その涙が国の礎となり、やがて再会の喜びに変わる日が来ることを信じたい。政治の力だけでは届かぬものがある。しかし、信念と祈りがあれば、奇跡は起こる。
宮司は祈る。どうかこの国が再び、「誰一人取り残さない日本」として立ち上がることを。総理の決意が、全ての国民の心に火を灯し、愛する者を取り戻す日へと導かれることを。
この国を思う心がある限り、日本は決して滅びない。