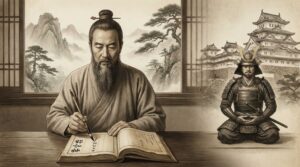七度生まれ変わっても、日本を護る覚悟

長野の山奥より、静かに思いを込めて
七度生まれ変わっても、この国を守りたい。
それが、神々に日々祈りを捧げる宮司としての、そして日本の大地に根ざして生きる一人の人間としての、揺るがぬ願いである。
この国に生を受け、この国の言葉に親しみ、この国の神々に日々額づいてきた宮司として、どうしても譲れぬ想いがある。
たとえば、「君が代」。これはただの国歌ではない。悠久の歴史を背に、万世一系の天皇の御代を寿ぎ、国の安寧を祈る、日本人の魂が込められた祈りの詞である。
耳で聞くのではない。心で詠むものだ。
この歌には、天と地とを結ぶ清らかな祈りと、祖先と子孫をつなぐ尊い血の流れが宿っている。
だからこそ、七度生まれ変わっても、宮司は「君が代」を護りたいと願う。
それは単なる旋律ではなく、この国の精神そのものだからである。
そして「日の丸」。あの白地に紅の円は、太陽の化身たる天照大御神の御光を象徴している。
白は清浄、紅は命の炎。この旗のもとに集い、時に涙し、時に誇りを抱きながら、宮司たちは代々この国を祈ってきた。
どれほどの国難に見舞われようとも、この旗を見上げれば、神々の御稜威(みいず)がそこにある。
だからこそ、七度生まれ変わっても、宮司はまたこの旗を仰ぎたいと願う。
そしてこの国を支えるための柱として、再び社に仕えたい。
さらに、宮司が生涯大切にしているものがある。「教育勅語」である。
これは明治天皇の大御心が記された、まさに日本人の道徳の原点である。
父母に孝を尽くし、兄弟に親しみ、夫婦は和し、友は信を持ち、己を慎み、博愛の志を忘れず、知を磨き、業を修め、義を重んじ、公に尽くし、国家に殉ずる覚悟を育む―この勅語の教えこそが、日本の柱であり、道しるべである。
ところが、現代の日本では、この教育勅語を「古い」だの「時代錯誤」だのと軽んじる声すらある。
だが宮司は断じて問いたい。この中のどこが間違っているというのか。
この国が荒廃し、親を顧みず、恩を忘れ、命の尊さが軽んじられるようになった今こそ、必要なのは、この勅語の精神であると確信している。
この国には、いま魂の再建が求められている。
経済や技術の話ではない。人としての根っこ、国としての背骨が揺らいでいる。
日本人とは何か、祖先とは誰か、子孫に何を残すのか―今こそ見つめ直すべき時が来ている。
宮司は想う。
あの楠木正成公が、いまこの国の姿をご覧になったならば、どれほど胸を痛められることか。
湊川に散ったその御心、忠誠の極みを今に伝えるその生き様を、現代の政治屋たちに誰が継いでいるのか。
そして国民は、かつての政治家のような人物を選び抜く覚悟を持っているのか。
悲しみと憤りが、交互に胸を打つ。
それでも、宮司は信じている。
この国には、まだ真心の人がいる。
まだ、静かにこの国の未来を憂い、祈り、行動しようとしている者たちがいる。
宮司は願う。
七度生まれ変わるとしても、またこの日本に生まれたい。
そして、君が代を歌い、日の丸を仰ぎ、教育勅語を若き世代に語り継ぎたい。
それが、宮司の祈りであり、誓いである。
長野の山奥の社より、ただ静かに天と国とを想いながら―。